
|
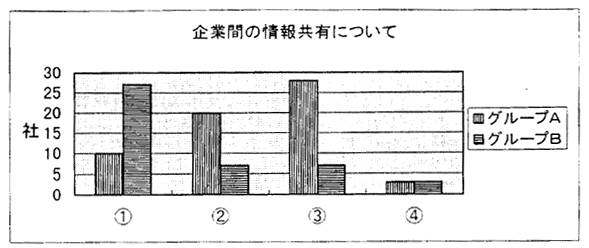
回答 A:61 B:43
回答傾向は前設問と同様の傾向がある。情報共有のメリットを認識する一方、ノウハウの流失を危慎する部分がある。ここでも情報が不足していることが大きい。
設問3.3:情報化、CALSに関連してこれまでの設問に係わらず、ご自由なご意見を
お書き下さい。
?業界のプロトコル、フォーマットの統一が必要。セキュリティ対策に留意が必要。
?アメリカの戦略に翻弄されず、日本独自のぺ一スが必要。
?メー力単独でできない、業界モデルの構築が必要
?商社の立場からメー力、顧客で情報ギャップがある、両者をみて対応する。
?LlNKSなど造船7社の動向は知っている。生産合理化など影響は出てくる
現状の業界で、これにどれだけ投資できるか経営上の検討が必要。
?情報化は分からない。どう取り組むか、具体例がほしい。
?CALSは今一つ分からない。
?親会社の指導に基づき検討する。
?弊社は規模が小さく、CALS構築と取引安定は直結しない。
?企業の独自性を保持できる共通化が必要
?海外事例で舶用メーカーがホームページを活用していた。業界ネット作りが必要
?客先・部品メーカの情報共有化のメリットはあるが、業界全体の情報共有は
ノウハウなどの問題があり進まない。
?対外制に公開情報は限定され、効果は薄い。内部制こは標準化、コスト低減に
効果は大きい
?舶用工、運輸省の推進にメリットがある。もくろみの明示がなければ進行は遅い。
特に中小企業は導入が難しい。
?共通部品的要素に限って進んで行くであろう。
?企業秘密の問題があり一般情報からの脱皮は困難
?営業支援、ホワイトカラー生産性向上、経営支援の3つをターゲットに情報化を推進
?舶用工業会のリーダーシップと早期指針のまとめが必要。
◎情報の共有化については、共有化のメリットと社内ノウハウの流失の問題がありどの様に線引きができるかがカギとなる。
◎業界としての標準化が望まれている。中小企業をも包含できる仕組みは、舶用CALSを推進する上で重要である。
◎多角的に業務改善をとらえていく必要がある。
◎舶用工業会としてのリーダーシップが望まれている。
前ページ 目次へ 次ページ
|

|